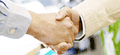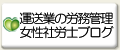おふぃま新聞 9月号
9月のおふぃま新聞は以下の内容でお送りします。
1.従業員の「資格確認書」が会社宛に届いた場合の対応
令和6年12月2日以降、従来の健康保険証が新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しています。
協会けんぽでは、令和7年7月下旬より順次、令和7年12月2日以降にマイナ保険証にて保険診療が受けられない人の資格確認書を、被保険者の自宅へと送付しています。協会けんぽの発送した資格確認書が、被保険者の転居等により宛先不明となって届かない場合もあることから、その場合は会社宛に送付するとされており、届いた場合は速やかに本人に配付してほしいとされています。
なお、これらの対応は令和7年4月30日時点の情報に基づき行われているため、既に退職等により資格喪失している人について、一覧表に掲載されていたり資格確認書が届いたりする可能性があります。
【厚生労働省「中医協資料;医療DX推進体制整備加算等の要件の見直しについて」】(PDFが開きます)
【厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用について」】
【全国健康保険協会「お知らせ(令和7年8月)」】
2.令和7年度地域別最低賃金額改定の目安が公表されました
令和7年8月4日に開催された第71回中央最低賃金審議会で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられ、公表されました。 目安通りに各都道府県で引上げが行われた場合の全国加重平均は1,118円で、全国加重平均の上昇額は63円(昨年度は51円)となります。これは昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額となり、引上げ率は6.0%(昨年度は5.1%)となります。
【厚生労働省「令和7年度地域別最低賃金額改定の目安について」】
3.「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について」の通達が公表されました
令和7年度税制改正において、健康保険法の被扶養者の認定対象者が19歳以上23歳未満である場合における取扱いについて、通達が公表されました。
認定対象者の年間収入に係る認定要件のうち、その額を130万円未満とするものについて、当該認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合にあっては150万円未満として取り扱うこと。
なお、当該認定対象者の年間収入の額に係る認定要件以外の取扱いについては、昭和52年通知と同じとすることとされています。
【厚生労働省「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について」(PDFが開きます)】
4.40歳から始める職場の転倒対策
東京労働局の調査によれば、休業4日以上の労働災害の約3割が転倒によるものでした。40歳代からは加齢に伴う身体機能の低下が徐々に始まるとされており、筋力低下やバランス感覚の衰え、視力の変化が転倒のリスクを高めます。
転倒災害は予防できる事故です。まずは通路の整理整頓、適切な照明、滑りやすい床面の改善など、基本的な安全対策を徹底しましょう。4S(整理・整頓・清掃・清潔)活動や危険の見える化、危険予知(KY)活動を取り入れ、従業員全員が危険箇所を把握しやすくすることも効果的です。
【東京労働局「令和6年労働災害発生状況」(PDFが開きます)】
5.独禁法上の問題につながるおそれのある荷主の行為
公正取引委員会の令和6年度の調査結果報告によると、現下の労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコスト上昇分の取引価格への反映の必要性について協議をすることなく取引価格を据え置く行為等が疑われる事案に関して、荷主100名に対する立入調査を行ったとしています。調査報告には、問題につながるおそれのある行為として挙がった事例が多数掲載されています。
【公正取引委員会「(令和7年6月24日)令和6年度における荷主と物流事業者との取引に関する調査結果及び優越的地位の濫用事案の処理状況について」】
6.9月からマイナ保険証がスマホでも利用できるようになります
現在、マイナンバーカードの保有者は、アプリのダウンロードによりマイナンバーカードの機能をスマートフォンで利用できますが、9月よりマイナ保険証の機能が搭載され、機器の準備が整った医療機関等で利用できるようになります。
【厚生労働省「9月からマイナ保険証がスマホでも使えます」】
【厚生労働省「資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)①」 】
【厚生労働省「資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)②」】
コラム
(所員O・記)
毎年、過去にない暑さの夏!を更新しています。
今年は、北海道で40度超の気温となりました。
この暑さは続くと考え、最近では、あえて北向きの家を選ぶ人も出てきているようです。
北向きの家は寒いというイメージがありますが、断熱材が普及してきた今では、冬の暖房費はそれほどかからないため、夏の冷房費が家を選ぶ基準になっているようです。
この暑さを有効に活用する方法と言えば、太陽光発電ですね。
郊外では以前は畑だったところにソーラーパネルがいくつも並んでいたりします。
しかし、都内のように家が密集しているところではなかなかソーラーパネルを置くこともできないので、最近ではビルの壁面が発電する建物もあるそうです。
暑い日差しで電気を起こし、その電気を使ったエアコンが冷房する。
これが正しいエネルギーの循環なのかな‥と疑問に思うところもありますが、そうも言ってはおられない暑さです。
by office-matsumoto | 2025-09-01